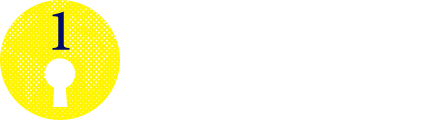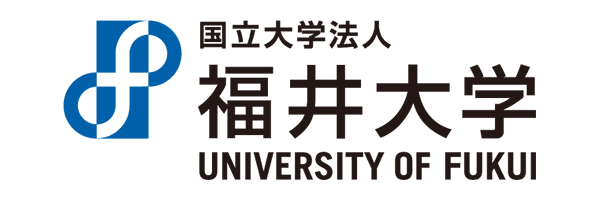語り合い
共に学びつながる場を
- 矢内 琴江
- YAUCHI Kotoe
- 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学 連合教職開発研究科 特命助教(社会教育学、ジェンダー論)
Profile
1985年、東京都生まれ。博士(文学)。2016年、早稲田大学大学院文学研究科教育学コース博士後期課程満期退学、2014年、同大学文学学術院総合人文科学研究センター助手、2017年、同大学文学学術院文学部教育学コース講師(任期付)を経て2019年4月から現職。
研究者詳細ページ
フェミニズムと女性の知
高校生の頃、「性同一性障害」についてレポートにまとめたことがきっかけで、これまで自分が受けてきた教育では性の多様性について知る機会がなかったことに疑問をもち、「人権とジェンダー」を考えるようになりました。
大学院では、カナダ・ケベック州の大学にある「フェミニズム・スタディーズ」の教育・研究機関に留学しました。きっかけは、性暴力をテーマにした同大学の夏期講座への参加でした。研究者も実践者も集まり活発な議論が交わされていたことに衝撃を受けました。
フェミニズムとは、性差別に疑問に思い、変えていきたいという意志をもち、実際に行動をおこしていく運動であり思想のプロセスです。帰国後、ケベックのフェミニズム・アートのギャラリーや、フェミニズムを実践のひとつの軸としたコミュニティ・オーガナイザーの学習グループの活動を分析する研究に取り組みました。抑圧的な状況を変えていこうとする女性たち自身やフェミニズムの実践のなかにこそ、性差別のない社会を創っていく知があると考えています。
ジェンダーの視点から語ることの意義
今、私が取り組んでいる実践の一つは、ゆる~く自由に「性」について、互いに耳を傾け合い語り合う「ゆるカフェ」です。学生たちと実行委員会をつくって、主体的に参加し、様々なアイディアを出したり、互いの経験や考えを丁寧に聴き合い語り合いながら運営しています。これまでの参加者からは、「今までジェンダーについて周りに話すことができなかったので話せる人たちに会えてうれしかった」「自分にはなかった視点を得た」といった声が聞かれています。
ジェンダーの問題を学ぶことは、その人らしく生きること、地域や組織の中で豊かな他者との関係を築く力につながります。誰もが、あるがまま伸びやかに生きていける社会を目指して。

ゆるカフェは2019年10月の第1回開催から、4回目を迎えました。今回のテーマは、2019年度NHK紅白歌合戦に物申す?
刺繍。夜ごと、こつこつと一針一針、ちくちくと心を込めて縫っています。